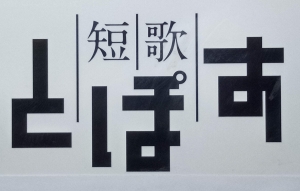月の浦政宗の夢遥かなり沖をゆくのは巨大タンカー 笹谷 逸郎
「月の浦」とくれば、政宗の家臣支倉常長のローマ派遣(※1)である。幕府の意向も受け外国との直接貿易を企図した。しかし、常長が帰国した時は家康も没し、時代はキリスト教禁制へと急転回しており、生類憐みの令を発令した徳川綱吉の時代。政宗の使節派遣は仙台領内においてすら忘れられていた。 作者はその歴史をサンファン館見学の時に幻視した。なお、「月の浦」は牡鹿半島コバルトラインの中ほどにあり、現地には支倉常長像が建てられている。
薬売り行李ひろげてふくらませ紙風船を「ホイ」とわたした 小 町
「置き薬」が無くなったのは何時の頃からだろう。いわゆる行商(富山のクスリ売り)である。どの家にもクスリ箱があり、定期的に各家庭をクスリ売り人が回って歩いた。使った分だけを代金として回収して行く仕組みは「信用売り」とも呼べるだろう。そして、子供には、おまけとして紙風船をくれたものだ。現代のようなおもちゃは無い時代、そんな素朴なものでも子供にとってはうれしいものだった。
コロナ禍が抜けきらずいて昼食時マスク外せばあんた誰かね 遊 心
新型コロナウイルスが収束して、「5類移行」なったのが二〇二三年五月、全世界を「パンデミック(※2)」という言葉が席巻した。それから、日常生活も元に戻ったと云えるようだが、マスクを付ける習慣は残っているようだ。会社組織、役所、警察などで発令したものが、そのまま定着してしまったようだ。マスクをすると守られている感覚になる。長期間マスク顔しか見ていない人がマスクを外したら誰かわからない、なるほどそうかも。変に納得させられた一首。
日陰道花の終わった藤棚に風鈴の音短冊ゆらす 智 絵
季節の風情を詠んだ。日陰道は作者の造語で、「日陰道」という固有名詞があるので、混乱するかもしれないので要注意だろう。情景としては、花が終わった藤棚に風鈴が吊り下げられている、その藤棚の中を風が抜けていく、風鈴が鳴り、短冊が揺れる。藤棚と風鈴の取り合わせが映像的である。
白つめ草生うる芝生に雀二羽しきり歌えば吾も唱和す 森 てい子
情景がわかりやすく詠われている。白つめ草、雀の取り合わせが「カワイイ」。白つめ草の愛らしい姿、雀のちょこちょこと動く様子とちゅんちゅんという鳴き声が相まって情景を効果的に浮かび上がらせる。それらに加えて作者が興にのって歌を口ずさんだ。かわいくて、愛らしくて、たのしい歌である。
郭公の啼く声きけばはるかなるふるさとを恋う父母を恋う 丹取 元
父母を恋う、は広い意味での「相聞歌」になる。辞典によると「相聞」は交渉、報告、訪問、音信などの意。つまり、互いに意志を伝えあうことであった。「万葉集」では、私情(親愛、悲別、慕情など)を伝えあった歌の意で、ほとんどが恋の歌である。
中州より匂ひ立ち来る若香魚の炭火を囲む名取川原に 原田奈津子
嗅覚の歌はあまり見ない。炭火で香魚を焼く匂いは香ばしくて食欲をそそられる。文法的に、「より」は格助詞 ①比較の意 ②否定表現とともに用いて他のものを排除してそれに限ることを示す。「こうするよりしかたがなかった」 ③動作・作用の起点を示す。この歌では③となる。
名掛町西口地下道廃止され昭和が消えるまたひとつまた 朝野クウー
仙台駅の西と東を結んだ地下道が、ガラス張りのエレベータ付の近代的な跨線橋の完成により廃止された。あの暗くコンクリートに囲まれた薄暗い照明の地下通路に若い頃、わたしはアウシュビッツのガス室に通じる印象を持った記憶がある。。
■次回歌会 九月六日(土) 午後二時
場所 青葉区中央市民センター
(鑑賞 朝野 クウー)